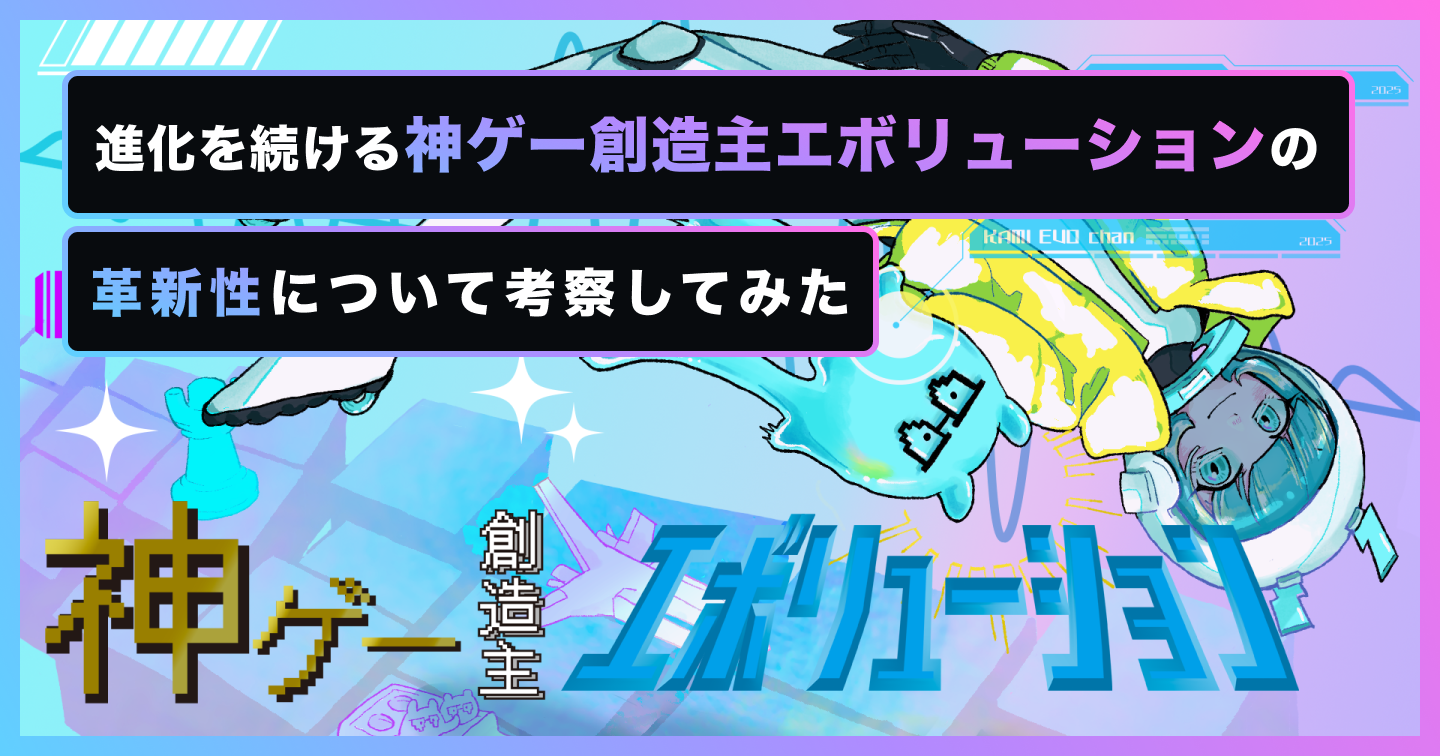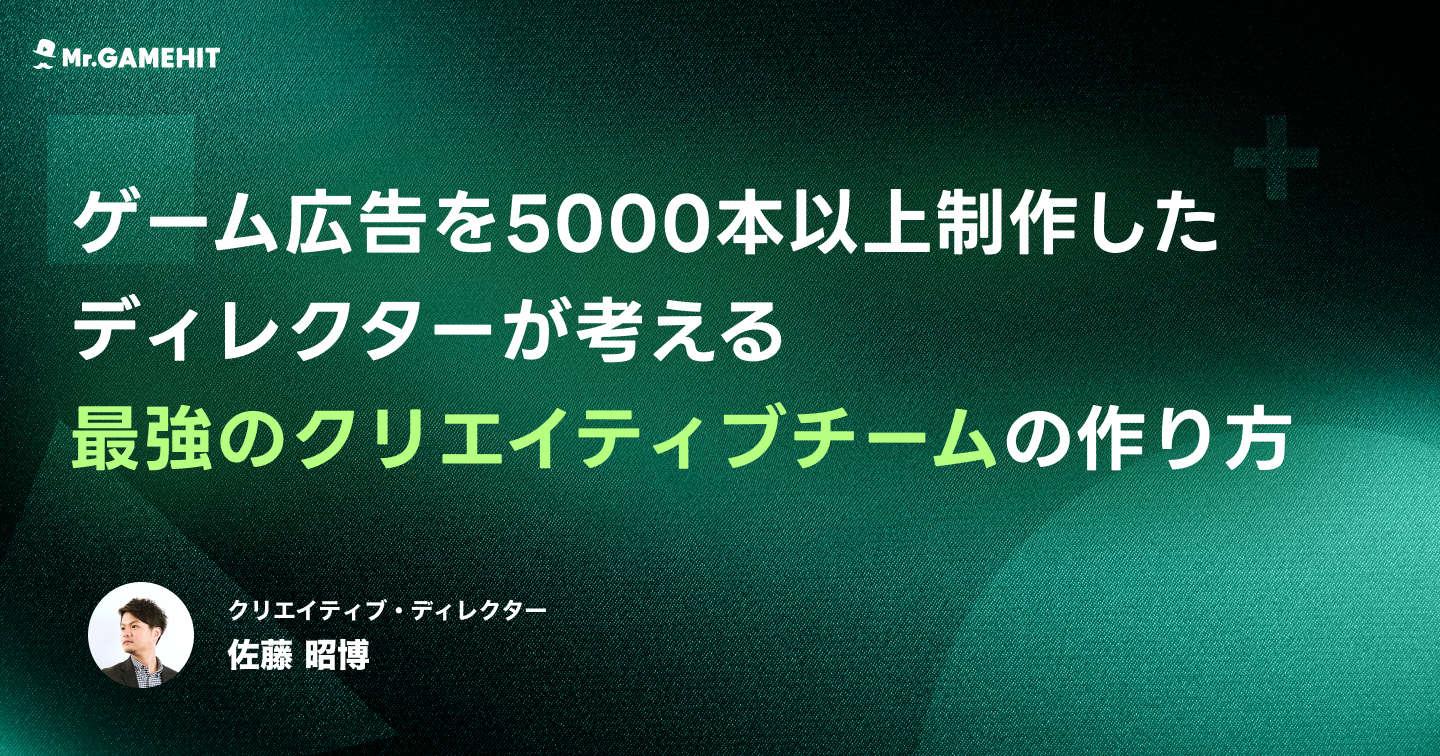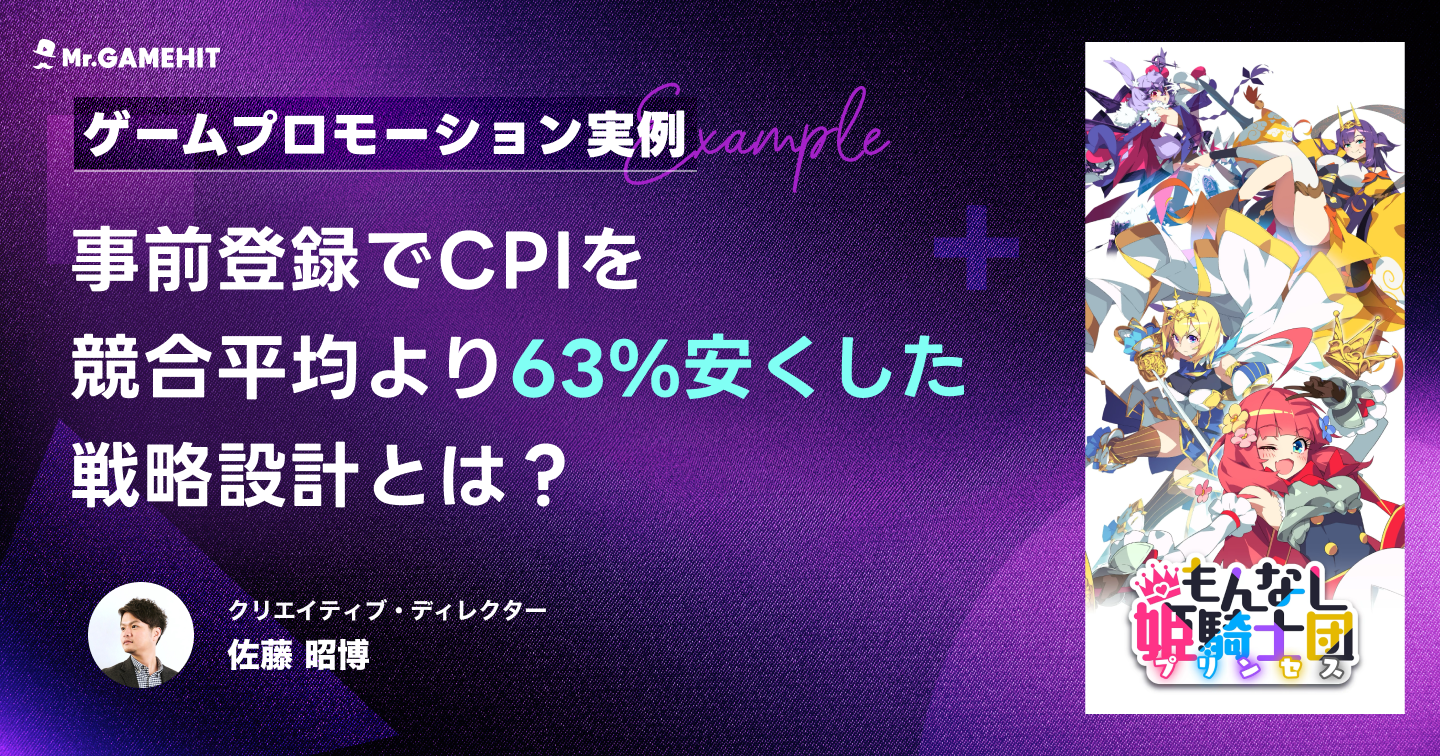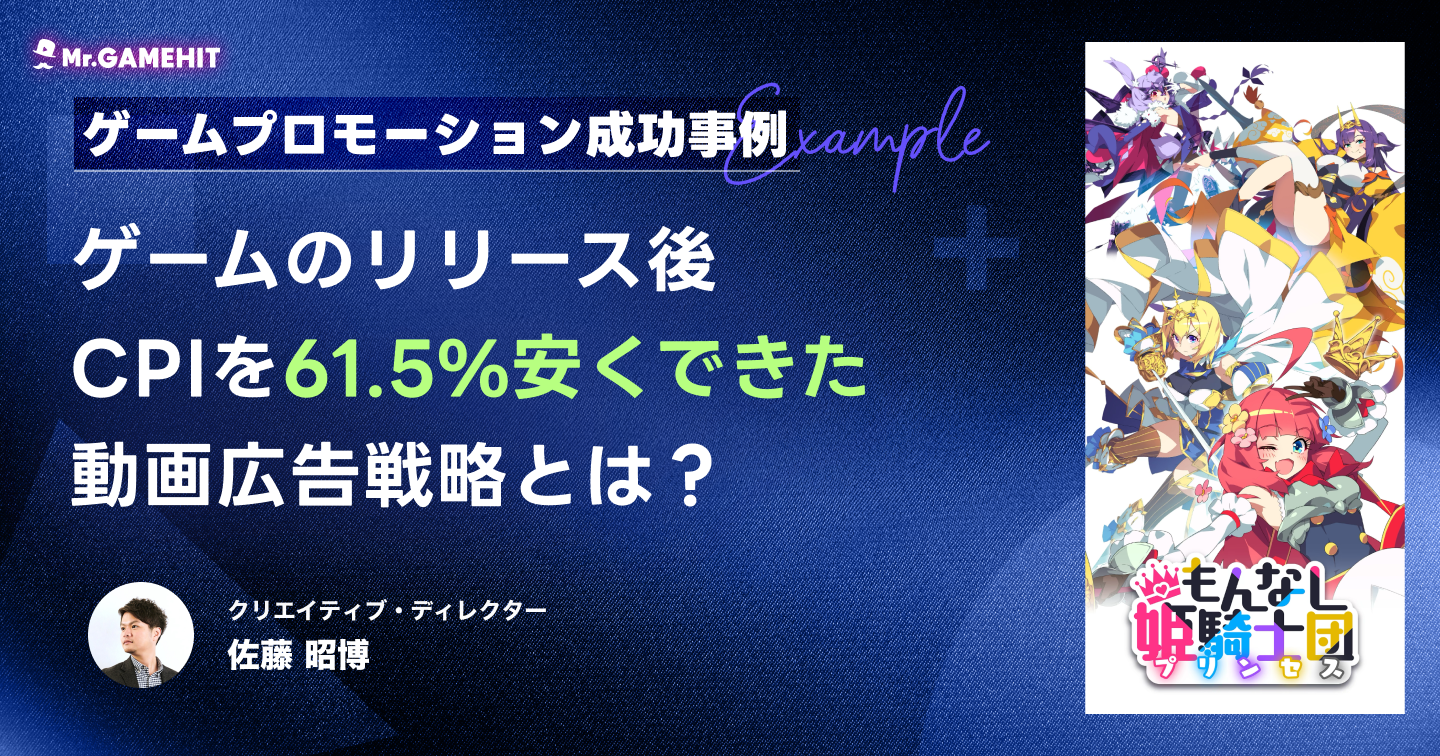こんにちは。Mr.GAMEHITのディレクター、毛利 優棋です。
今年も多くのインディーゲームイベント・コンテストの開催が予定されていますが、今回は回数を重ねるごとに様々な進化を見せ、注目度が高まっている「神ゲー創造主エボリューション」を取り上げてみました。改めてどんなコンテストなのか、筆者が選ぶ注目ポイント・エントリーの際に皆が気にしている「革新性」とはなんなのか、2025年度の開催で進化している点を本記事でお伝えします。
※執筆にあたり実行委員長をはじめ、審査員やメンターの皆様、昨年度のファイナリスト作品のクリエイターにWEBミーティング形式でのインタビュー、メールでのご質問をさせていただきました。
■エントリーについて
エントリーの締め切りは(2025年5月16日(金)15時まで)となっておりますのでもし、「革新性」という審査基準がハードルとなっているクリエイター、悩んでいるクリエイターの背中を後押しすることができれば幸いです。
2025年 神ゲー創造主エボリューションのエントリーはコチラ

神ゲー創造主エボリューションとは?
「神ゲー創造主エボリューション」とは若手ゲームクリエイターを発掘し、育て、共に新しい時代を切り拓いていくためのプロジェクトです。 “コンテスト” ”番組放送” “オンラインコミュニティ”の3軸で、たくさんの人を夢中にさせ魅了するゲームクリエイターの発掘・育成を目指しています。
2024年度より日本ゲーム大賞の“アマチュア部門”と“U18部門”を継承したことでより一層、エントリー作品の厚みも増して「革新的な作品」の応募が見られるようになったと筆者は感じました。
まずは筆者が過去にコンテスト作品の試遊、イベント参加の際に感じた注目ポイントをいくつかピックアップしてご紹介いたします。
個性的な作品、自由な発想の作品
昨年は1次審査を担当させていただいたのですが、本当に幅広い応募作品がエントリーされており自身の担当する作品を一通りチェックした後に楽しすぎて担当外の作品もついつい見てしまいました!
応募段階でこんなにも魅力的なのに、その中から選出されたタイトルたちが持っている独自性、目を引く要素は凄く刺激的だと思うので審査突破の作品はもちろん、応募作品も機会があれば是非とも実際に触れてみてください!
期間中に見せる作品達の劇的な変化
神ゲー創造主エボリューションはエントリーの後に審査を通過すると段階的にイベント出展やブラッシュアップが行われます。特に2次審査を通過した後から3次審査、ファイナリスト発表、そして最終の決勝大会までの期間で「劇的な変化を見せる作品」、「大化けする作品」がこれまでも複数見られました。コンテストで選出されたタイトルを追うことで作品がより魅力的に変化する様子をリアルタイムで追うことができる楽しみ、わくわく感を味わえるはずなので個人的に推しポイントと考えます。
革新性に気づいた(発見した)際の驚きや喜び
当然ですがクリエイターは自分たちの作品のどんな部分が革新的なのかを考えてエントリーしています。しかし、知識や経験が豊富な審査員の方々、メンターの方々による分析でクリエイターですら気が付いていなかった「革新性」が発見されることも少なくはありません。
これまでの物の見方が変わる瞬間、皆が気付いていなかった「革新性」にスポットが当たった瞬間、更なる創造と進化の可能性が示された時の驚きや喜びが生まれる瞬間はきっと誰かと共有したくなるはずでなのでぜひ注目してみてください。
注目ポイントを自身で色々と考えている中で、改めて「神ゲー創造主エボリューション」が持つ魅力的なポイントについて考えることができたのですが…個人的にはまだまだ推したいポイントはでてきます。きっと人それぞれ“推したいポイント”は色々あると思うので、この部分については今後も機会があれば意見を聞いて見識を広げていきたいと考えています。
「革新性」について実際に聞いて考察してみた
ここまでは「神ゲー創造主エボリューション」がどういったコンテストで、どんな注目ポイントがあるかを紹介しました。ここからは冒頭でも書いている通り審査基準にある「革新性」について触れていきます。
評価基準の「革新性」ってなんだろう?
-革新性の定義 ※AI による概要-
革新性とは、既存の概念や方法論を打破し、新しい価値を生み出す能力や状態を指します。
何となく文字にしてみて理解ができるような気がするけれど、はっきりとした基準が分からない…この「革新性」という部分に自信が持てなくてエントリーに踏み切れないという人もいるかもしれません。
もしかしたらその作品は“世界を変える可能性を秘めている”のに!
「革新性」がなんなのかわからなくて悩んでいる。そんな勿体ないを少しでも減らしたい面白いゲームに1作品でも多く出会いたいという個人的な想いもあり、改めて「革新性」という言葉を他の人たちがどんな風に考えているのか、実行委員長・審査員・メンターの皆様や参加をしたクリエイターに「革新性」とは何なのかという疑問を投げかけ、答えていただいた中で印象に残った部分をご紹介します。
実行委員長・斎藤直宏さん
(東京国際工科専門職大学 デジタルエンタテインメント学科 学科長)
筆者は「革新性」を得るためには新しい技術は必須なのかという疑問を抱えていたため、今回「神ゲー創造主エボリューション」実行委員長の斎藤さんに技術面からの質問をいくつかさせていただきました。
お話の中で確かに革新性に繋がる技術もあるかもしれないけれど、技術は道具でしかないので新しい古いは特に関係なく、その道具を「どう使って遊びに昇華していくかが大切」とおっしゃっていました。お話の中で「新しい技術=革新性のコアではない」あくまでどう使うかアイディアが大切であるという点に気付かせていただきました。
特別審査員・米光一成さん
(デジタルハリウッド大学 教授)
米光さんにはメールにて革新性について質問をさせていただきました。
・米光さんの考える革新性とは
100年後に革新的だった!と判断されるものは、現在の我々の眼には、おそらく何だかわからないものになってしまうと思うので、現在の我々の目を覚まさせる、これか、この手があったか!と気づかさせるものでないと「革新性がある」と判断できないんだろうな、と。
・神エボに参加をした際に、どのような部分で革新性を感じるのか
昨年のグランプリ作品『吉見君はゲームばかり』を例に挙げて、勇者が世界を救うのでもなく、そして王様は出てくるけれど途中の道端みたな権威性のない場に出てくるゲームで、「世界救出妄想や権威主義的なゲーム観を否定した革新的なゲームだ!」とか評することができそうな内容ですが、作ってる本人たちは「イケメンといっしょにゲームをやりたい!」という初期衝動で作っていたようだ。でも、その初期衝動が大切で、それを貫いて作ったことによって他者におもねらない革新的なものになったのだと分析されています。
また、審査員としての視点より
神エボは、制作過程を並走する審査方式です。最初の構想段階では、もしかして革新的なものになるのでは?と思っていたゲームが、爆発が派手なだけの何かありがちなゲームになったことがありました。
製作者本人に「あれ、こんな爆発ゲーが作りたかったの?」と聞くと、「違うけれど地味だから爆発を入れて派手にしたほうがいいというアドバイスに従った」と答えが返ってきました。
アドバイスは聞いたほうがいいけど、取り入れるかどうかは自分で判断しないと、最初にもっていた革新性を失っちゃう。作りたいものは何なのか、最初に自分を突き動かした「何か」が結果として革新性につながることを信じる力が大切だよと、審査をしていると実感します。
このようなメッセージも頂いており、最初に自分を突き動かした「何か」や「初期衝動」を大切にすることが結果として革新性に繋がるのではないかと筆者は感じました。
特別審査員・谷口暁彦さん
(多摩美術大学 メディア芸術コース教授)
昨年の大会を振り返って感じた変化や傾向のお話の中で、これまではゲームというコンテンツ内で革新的なものを目指そうとしていた傾向があったけれどゲーム実況やチャット・ボイスチャットをしながらという「現代のゲーム環境や状況をモチーフ」にする作品が出現してきたというお話が印象に残りました。
日々進化するゲーム環境に慣れてしまいがちですが、“環境の変化=革新性”に繋がりやすい要素の1つだと気付かされました。また、谷口さんの考える「革新性」という部分では「一見ゲームに見えないけれど…みたいな要素も結構大事」とおっしゃっていたので、エントリー予定の作品がちょっと尖ってるかもと感じていても思い切ってどーんとぶつかってみるのもアリだと思いました!
メンター、一次、二次審査員・簗瀬洋平さん
(Unity Technologies Japan)
昨年のグランプリ作品である『吉見くんはゲームばっかり』が自分たちの技術レベルでは実現困難なことに対して、“プロの人では想像できない方法”でアプローチして解決したお話や、ファイナリスト作品『SPACE INVADIANS』の持つゲームに対してのアンチテーゼへの向き合い方のお話を聞く中で、メンター・簗瀬さんの考える革新性は「本当に自分がやりたいことやって作ってるもの」、「制約などに縛られず枷がはずれているもの」、「チャレンジしなければ生まれないもの」であると感じました。
ゲーム制作のプロフェッショナルがしないアプローチ方法にもしかしたらヒントがかくれているのかもしれない…もっと色々なお話を今後も聞かせていただきたいと思います。
クリエイター・國富空太さん
(HAL大阪 チームO.I.L.)
昨年のファイナリスト作品『目隠シ』のチームリーダーである國富さんには審査基準の「革新性」について、どんな風に考えているのか、エントリーの際の対策や制作秘話なども聞かせて貰いました。
『目隠シ』はWEBカメラの顔認証機能を使い、プレイ中に目をつぶるという斬新なホラーゲームであるですが、エントリー期日が伸びたお陰で参加できたというお話や、エントリー時からグランプリを狙って企画されていたという点が凄く印象的でした。
最大の悩みどころである審査基準の「革新性」に対して独自のアプローチをしており、ゲームバランスの割合の数値化、過去に審査員がどんな傾向で評価をしているか等の分析を行っている点などアプローチの面が非常に面白かったです。
2025年もエントリーを予定しているとの事だったので新作もぜひとも注目です。
筆者が感じた「革新性」とは?
これまで「革新性」という言葉にどうしても引っ張られてしまう所は正直ありましたが、色々な方のお話を聞きつつ過去の作品などを振り返ってみて、まずは自身がちょっとでも「革新性」があると思ったら「神ゲー創造主エボリューション」のエントリー基準は満たしているのではないかと感じました。
まだエントリーが少ない特殊デバイス系、VR作品、アートツールや工業系の技術を使った作品などは未開拓の状態なので「革新性」という条件をクリアしやすいのかもしれないし、作品として出てきた時にどんな風に評価が行われるのかも凄く気になります。
もしかして、この技術を使ったアイディアはゲームとして面白いかもしれない、この遊び方は面白いかもしれないと思ったら選考基準に縛られず迷わずにエントリーをしても良いと思います!
筆者が選ぶ過去タイトルがもつ革新性の紹介
ここでは過去エントリー3作品の中で実際にプレイして感じた革新性をご紹介いたします。
SPACE INVADIANS
『SPACE INVADIANS』は弾を撃たない(撃てない)シューティングゲームです。突如現れたUFOの1つがビルに激突し、主人公が彼らの船に乗り込んでいくストーリーの本作ですが、初見でプレイした際はまったくもって何なのか理解ができずに困惑したことを今でも覚えています。
のちにその理由が発覚し、これまでプレイしてきたゲームの概念を覆された衝撃の事実に「革新性」という言葉を感じずにはいられませんでした。
これは概念の外側からの築きという部分で衝撃が大きすぎて人生の中で忘れられない1本になっています。
目隠シ
『目隠シ』は顔認証システムを使うことで現実とゲームの世界の垣根を超えた恐怖体験ができるホラーゲームです。
ゲームの中で襲われる怪異をやり過ごすために目を瞑るのですが…目を瞑ることで視覚に変わって自身の脳内が色々なことを想像させてくれるので本当に怖い、リアルの世界まで浸食された感覚はぜひ味わって欲しいし、味わったらきっと誰かと共感したくなりますよ!
ホラーゲームが苦手だけど、怖いもの見たさでついついやっちゃう…そんな仲間とはぜひプレイした上で恐怖体験を分かち合いたい。目を瞑っても恐怖、開けてても恐怖を味わえる点は本当に革新的だと感じました。
ゾウだけが解けるパスワード
『ゾウだけが解けるパスワード』はプレイヤーの指をゾウの鼻に見立てて遊ぶパズルアクションゲームです。1人プレイでじっくりやり込んでも良いし、2人プレイでちょっぴりドキドキしながら遊ぶも良し!
スマートフォンを見つけた像になって様々なパズルをクリアする本作は2023年のグランプリ作品です。直前まで『指・ひも・カギ』というタイトルだった本作は、コンテストの中でより洗練されて完成度が高められ、名前まで変わるという様々な角度からのエンターテインメント性も含めて「革新性」を演出し、感じさせてくれたタイトルです。
第4回も進化(エボリューション)が止まらない!
2025年で4回目となる「神ゲー創造主エボリューション」ですが、回を重ねるごとに様々な面で進化を見せています。2024年の例を挙げると、日本ゲーム大賞「アマチュア部門/U18部門」を受け継ぐ形での規模拡大、原宿の会場で行われた2日間にわたるファイナリスト作品やノミネート作品、学生作品の試遊展示とこれまで以上に多くのユーザーに向けてゲームの持つ魅力が発信できるコンテスト・イベントに成長を見せています。
2025年は「神エボlab(ラボ)」が始動!?
2025年はゲームをまだ作ってはいないけれど、自身が今研究しているテーマ、様々な技術、アート分野、社会課題などもしかしたらゲームになるかもしれない、ゲームにすることで解決できるかもしれないというアプローチができる場所が誕生する予定です。
誰もがゲームを作ることができる時代に突入しているからこそ、ゲームをまだ作っていないクリエイター、技術者、研究者、アイディアをもつ発案者が交じり合い「新たな革新性を生み出す別アプローチの方法の1つ」になり得るか。
今回より始動する、「神エボlab(ラボ)」が今後どういった動きを見せるか、国内で稀有なコミュニティーの1つとして注目です!その他にもまだまだ未発表の面白いコンテンツが用意されているようなので発表を楽しみに待ちつつ、キャッチした際には発信させていただきます。
まとめ
今回は「神ゲー創造主エボリューション」の審査基準である「革新性」について色々なお話を聞かせていただき、私なりに考えて文字に残す機会をいただきました。
当然ですがすべてを理解すること、解き明かすことはできませんでしたが、それでもこのコンテストが「誰も見たことがない面白いゲームを作る」という揺るぎない根幹の部分に触れることができたように思えます。
今年で第4回となる「神ゲー創造主エボリューション」はこれからスタートとなりますので、今までも追っていただいている皆様も、初めて知った皆様も面白いゲームの誕生をリアルタイムで追うことができるゲームコンテストとして是非ともご注目ください。
最後となりますが、慌ただしいスケジュールの中でご協力していただいた皆様にこの場を借りて改めまして御礼申し上げます。
「ご協力、本当にありがとうございました」
【告知など】
2025年の「神ゲー創造主エボリューション」は2025年5月16日(金)15時までエントリーが可能となります。
「神エボlab(ラボ)」のエントリーは6月13日(金)15時までとなりますので、詳細ページと専用エントリーフォームをぜひチェックしてみてください!
★アーカイブ★
2024年に開催された本大会の様子は、公式YouTubeチャンネルとニコニコ生放送でアーカイブ配信されているのでぜひチェックしてみてください!
「Mr.GAMEHIT」はゲーム業界に特化した動画広告サービスを提供しています。AAAタイトルはもちろん、インディーゲームにおいても多くの制作実績を有している“ ガチなゲーマー集団 ”がユーザーに刺さる動画制作、広告の効果改善、プレイヤー数の増加をサポートしております。
ゲーム動画広告でお悩みの方はお気軽にご相談ください。